はじめに
家計簿をつけたいけれど、「毎回入力が面倒」「続かない」と感じたことはありませんか?
そんな悩みを解決してくれるのが、**家計簿アプリ『マネーフォワード ME』**です。
銀行口座、クレジットカード、電子マネー、QR決済などを自動で連携し、
手入力なしで支出を自動記録・グラフ化してくれるため、誰でも簡単にお金の流れを見える化できます。
この記事では、初心者でも迷わず使いこなせるように
連携設定 → 自動仕分け → 予算設定 → 現金入力
の順で、わかりやすく解説していきます。
マネーフォワードの魅力とは
マネーフォワード MEの最大の魅力は、圧倒的な自動化です。
銀行やカードを登録しておくだけで、入出金がリアルタイムに反映され、
自動で「食費」「光熱費」「娯楽費」などに分類されます。
スマホ1つで全資産を一目で把握できるため、
「今月あといくら使えるか」がすぐわかるのが最大の強み。
無料プランでも十分に便利ですが、
有料のプレミアムプランでは
-
連携口座の上限なし
-
データの自動更新頻度アップ
-
広告非表示・詳細な分析機能
が利用でき、より正確な家計分析が可能です。
初心者でも安心の使いやすさ
マネーフォワード MEは、初心者でも直感的に使える家計簿アプリです。
アプリが自動で収支を仕分けしてくれるので、難しい操作は不要。
また、予算を設定すれば「今月あといくら使えるか」が一目でわかります。
現金払いの場合も、手入力で簡単に登録可能。
レシート撮影機能を使えば、入力の手間も最小限にできます。
さらに、複数の家計簿を作成できるため、
「個人用」「家族用」「副業用」などを分けて管理することも可能です。
使い始めて3日で“家計の全体像”が見える——これが人気の理由です。
AIによる自動入力で“入力ゼロ”を実現
マネーフォワード MEは、AIによる自動入力機能も充実しています。
レシートをスマホで撮影するだけで、金額や店舗名を自動で読み取り、
そのまま家計簿に反映されるため、入力の手間がほとんどありません。
また、電子明細データの自動取り込みにも対応しており、
ネットショッピングや電子決済の記録も漏れなく集約できます。
**「入力しない家計簿」**を実現できる点が、他の家計簿アプリとの大きな違いです。
他の家計簿アプリとの違い・連携
マネーフォワード MEは、単体でも非常に優秀ですが、
他のアプリと組み合わせることでさらに便利になります。
たとえば、夫婦で家計を共有したい場合は「OsidOri(オシドリ)」と連携して
共同家計簿として使うことも可能。
また、レシート特化型アプリ「Receipi」や「Zaim」との併用で、
細かい支出分析も精度が上がります。
複数のアプリをうまく使い分けることで、
「家計簿が続かない」「記録が漏れる」といった悩みを解消できます。
ビジネス利用にも強い!副業や確定申告の味方
マネーフォワードは家計簿アプリとしてだけでなく、
個人事業主・副業ユーザーにも人気です。
「マネーフォワード クラウド会計」と連携することで、
請求書作成や経費の仕訳が自動化され、確定申告の手間を大幅に削減できます。
たとえば、売上を登録すると仕訳候補が自動で反映され、
入金時には請求書との照合(消込)まで自動で行われます。
✅ 家計と事業用を分けて管理できる
✅ 仕訳・経費処理が自動で完了
✅ 税理士との共有もスムーズ
といった利便性から、個人事業主やフリーランスにも選ばれています。
マネーフォワードMEの使い方:基本操作から応用まで

マネーフォワードMEは、個人の家計管理に特化したアプリです。
金融機関との自動連携によって、毎日の収支を自動記録・グラフ化。
ここでは初心者でも安心して使い始められるよう、
初期設定から応用テクニックまでを順番に解説します。
ステップ①:アプリをダウンロードして連携設定を行う
まずは「マネーフォワードME」アプリをダウンロード。
無料で利用でき、iPhone/Androidのどちらにも対応しています。
初回起動後は、アカウントを作成して
銀行・クレジットカード・電子マネーなどを連携設定します。
連携方法は簡単で、
「連携する」→金融機関を検索→ログイン情報を入力
するだけ。
ほとんどの銀行・カードに対応しているため、誰でもすぐに始められます。
💡 ポイント
マネーフォワードは「連携できる金融機関数」が業界トップクラス。
主要銀行から楽天カード・PayPayまで幅広く対応しています。
ステップ②:確定申告スイッチを活用しよう(副業・個人事業主向け)
副業収入がある人は、「確定申告スイッチ」をONにしておくのがおすすめ。
支出データをクラウド確定申告に連携できるため、
確定申告書類の作成が驚くほどラクになります。
🔸 家計簿と経費管理を一括で行いたい人
🔸 副業の支出を自動で仕訳したい人
に特に効果的です。
※設定はスマホアプリ版のみ対応なので注意しましょう。
ステップ③:現金支出を手入力で管理する方法
キャッシュレスが普及しても、現金払いは意外と多いもの。
マネーフォワードMEでは、現金支出も手入力で簡単に記録できます。
コツは次の3つです:
1️⃣ レシートをもらったらすぐに入力する
2️⃣ カテゴリ(食費・交通費など)を正確に選ぶ
3️⃣ 週1回は財布の中身とアプリ残高を照合する
こうすることで、記録漏れや誤差を防げます。
家計簿アプリで「現金が合わない」と悩む人の多くは、
その日のうちに入力しないことが原因です。
ステップ④:自動連携の仕組みとデータ管理のコツ

マネーフォワードMEの最大の強みは、自動連携による精密なデータ収集です。
銀行・カード・電子マネー・ポイントなど、ほぼ全ての取引が自動で反映されます。
ただし、
-
メンテナンス中の金融機関
-
パスワード更新後の未再認証
などのケースでは「連携できない」「反映されない」ことがあります。
この場合、ログイン情報を再入力するか、手動更新すれば解決できます。
→ この内容は次回の記事「マネーフォワード連携トラブルの解決法」で詳しく解説します。
ステップ⑤:予算設定と家計分析の使い方
支出を減らしたい人は、まず予算設定を活用しましょう。
マネーフォワードMEでは過去の支出データをもとに、
カテゴリ別の平均支出を自動提案してくれます。
毎月の「予算と実績」を比較することで、
「外食費が増えた」「通信費が下がった」といった傾向がひと目でわかります。
💡コツ:固定費(家賃・保険・通信)は定額化、
変動費(食費・娯楽)は目標を10~20%下げて設定する
こうした“見える化”を続けることで、
無理なく貯金体質へ変化できます。
自動連携のメリットと注意点
マネーフォワードMEの最大の魅力は、自動連携による正確で継続的な家計管理です。
銀行口座やクレジットカード、電子マネーを一度登録すれば、以後の入出金が自動で反映され、手入力の手間がなくなります。
✅ 手入力によるミス・記録漏れを防げる
✅ 複数の口座・カードをまとめて管理できる
✅ リアルタイムで資産全体が見える
このように、家計簿を“つける”から“自動で整う”に変えるのが、自動連携の最大のメリットです。
一方で、注意点もあります。
連携時には銀行やカードのログイン情報(ID・パスワード)を入力する必要があるため、
セキュリティ対策が十分にとられているかを確認しましょう。
また、金融機関によってはメンテナンス中や認証方式の変更により、
一時的にデータが「反映されない」「連携できない」こともあります。
特に海外口座や特殊な取引(外貨・仮想通貨など)は、カテゴリ分類が誤認される場合があるため、
月に一度は連携状況を確認しておくのがおすすめです。
連携データの管理と活用方法
自動連携で取得されたデータは、マネーフォワードMEが自動で「食費」「日用品」「固定費」などに分類してくれます。
しかし、より正確な家計簿にするためには、月1回の見直しが重要です。
特に以下のようなケースでは、手動修正が必要になることがあります。
-
仕事関係の支出(事業用経費)と私的支出が混在している
-
家族や友人への立て替え、ギフト支払いなど特殊な取引
-
カテゴリが自動で誤認された(例:外食→食費扱いなど)
これらを定期的に整理することで、正確な「支出構造」が見えるようになります。
また、マネーフォワードMEの家計分析機能を活用すれば、
毎月の支出傾向・貯蓄率・資産推移をグラフで自動表示できます。
💡活用ポイント
月次レポートで“支出のクセ”を把握
年次レポートで“貯蓄率の変化”を分析
家族共有機能で“世帯全体の見える化”を実現
こうしたデータを定期的にチェックするだけで、
「何となくお金が減っていく」を「数字で把握できる家計」に変えられます。
自動仕訳機能の設定と活用

マネーフォワードには、取引内容を自動で仕分けしてくれる**「自動仕訳機能」**があります。
これは「どの支出をどのカテゴリ(勘定科目)に入れるか」をAIが判断して分類してくれる機能です。
例えば、
-
コンビニ支払い → 食費
-
楽天モバイル → 通信費
-
Amazonでの備品購入 → 事業経費
といったように、支出内容を自動で整理してくれるため、
毎月の家計簿や経費入力の手間が激減します。
自動仕訳ルールの基本設定
自動仕訳の精度を上げるには、「仕訳ルール」を自分で設定しておくのがおすすめです。
設定画面では、「取引先名」や「支払い内容」に応じてルールを作ることができます。
例)
「セブン-イレブン」→ 食費
「ENEOS」→ ガソリン代
「Amazon」→ 日用品費
一度設定すれば、次回以降は自動で同じカテゴリに振り分けられます。
これにより、AIが誤分類するケースを減らし、自分専用の最適化された家計簿を作れます。
仕訳ルールの優先順位と運用のコツ
複数のルールが重なる場合、マネーフォワードは「上位にあるルール」を優先して適用します。
そのため、**よく使う支出先(スーパー・電気・スマホ代など)**は優先順位を高く設定しておきましょう。
また、季節限定の支出(ふるさと納税・年末セールなど)は、
期間終了後にルールを削除することで、データがすっきり保てます。
💡コツ:
最初の1ヶ月は「AIの自動仕訳+自分の修正」で学習を進める
よく使うお店やサブスクをルール登録しておく
不要になったルールは定期的に削除
このように少しだけ設定を工夫すれば、
マネーフォワードMEは放っておくだけで家計簿が整うアプリになります。
ビジネス利用・副業利用の場合
副業や個人事業で使う場合は、
「マネーフォワード クラウド確定申告」と連携することで、仕訳データをそのまま経費処理に反映できます。
たとえば、
-
取材の交通費 → 旅費交通費
-
サーバー費用 → 通信費
-
広告費 → 販促費
といったように、自動仕訳のルールを作っておけば、
確定申告時に手入力の手間をほぼゼロにできます。
CSVデータのエクスポート(バックアップ)
マネーフォワードMEでは、家計簿データをCSV形式で出力できます。
これは、Excelなどで開ける表形式のデータで、
「月ごとの支出」「カテゴリ別内訳」「銀行残高の推移」などを確認・保存するのに便利です。
💡バックアップのメリット
スマホを紛失してもデータを復元できる
長期間の家計データを分析できる
他アプリへの乗り換え時にも再利用できる
出力方法は、アプリの「設定」→「データ管理」→「エクスポート」を選択するだけ。
家計簿データを自分のパソコンやクラウド(Googleドライブなど)に保存しておくと安心です。
CSVファイルを活用した分析
CSVデータをExcelやGoogleスプレッドシートで開けば、
「支出の多いカテゴリ」や「季節ごとの出費傾向」を細かく分析できます。
例えば:
-
夏の電気代・水道代を前年と比較する
-
食費・外食費の増減をグラフ化する
-
副業の経費をカテゴリ別に集計する
といった分析が簡単にできます。
マネーフォワードMEのグラフよりも細かく分析したい人にはおすすめの方法です。
複数端末でのデータ共有・引き継ぎ
スマホを機種変更した場合でも、同じアカウントでログインすればデータは自動で引き継ぎされます。
ただし、古い端末でログアウトする前に、念のためCSVバックアップを取っておくと安全です。
また、家族と共同管理したい場合は、
クラウド(Googleドライブ・Dropboxなど)にバックアップを保存して共有すれば、
お互いのパソコンやスマホで同じデータを確認できます。
データを活用して“家計を見える化”する
CSV出力した家計簿を定期的に見返すことで、
「去年よりも光熱費が上がっている」「固定費が思ったより高い」といった気づきが得られます。
このように、マネーフォワードのデータは単なる記録ではなく、
お金の流れを改善するための材料として活用できるのです。
レシート撮影と現金管理のテクニック

マネーフォワードMEは自動連携が便利ですが、
現金で支払った分やレシートをもらった支出もきちんと管理しておくことが大切です。
現金の支出を放置すると、
「アプリ上の残高」と「実際の財布の中身」がズレてしまい、
せっかくの家計簿が正確に機能しなくなります。
そんな時に役立つのが、レシート撮影機能と手入力機能です。
ここでは、無理なく継続できる現金管理のコツを紹介します。
レシート撮影の正しい使い方
マネーフォワードのレシート撮影機能を使えば、
スマホのカメラで撮るだけで金額・日付・店舗名を自動入力してくれます。
撮影精度を高めるには、以下の3つがポイントです👇
✅ 明るい場所で撮る(照明や影に注意)
✅ レシートを平らにして全体を写す
✅ 受け取ったらすぐ撮影(文字が薄くなる前に)
特に熱転写レシートは時間が経つと消えるため、受け取った直後がベストタイミングです。
撮影後はアプリが自動で金額を読み取るので、金額・カテゴリだけ確認して保存すればOKです。
💡ワンポイント:
スーパーやドラッグストアなどレシートが長い場合は、
「上半分」と「下半分」に分けて撮影すると精度が上がります。
現金の支出を正確に把握するコツ
現金支出の記録は、習慣化がカギです。
面倒に感じる場合は、以下のような方法を試してみましょう。
-
財布に「現金支出メモ」を入れて、1日1回まとめて入力
-
アプリのウィジェットをホーム画面に追加し、即入力できるようにする
-
支出のたびに「音声入力」や「レシート撮影」で簡単登録
また、週に1回は財布の残高とアプリの現金残高を照合しましょう。
少額でもズレをそのままにすると、後で全体の収支が合わなくなります。
キャッシュレスと現金のバランス管理
キャッシュレス全盛の今でも、
現金を使うシーン(子どものお小遣い、屋台、自治会費など)はまだ多くあります。
おすすめは、
✅「現金は変動費(食費・娯楽費)」、
✅「キャッシュレスは固定費(光熱費・通信費)」
というように使い分けルールを決めること。
このように分けておくと、
「どこに使いすぎているか」が一目で分かるようになります。
電子マネーを現金でチャージした場合は、
「現金 → 電子マネーの移動」として記録しておくと、重複記録を防げます。
レシート管理を“楽しみながら続ける”コツ
家計簿が続かない最大の原因は「記録が面倒だから」です。
でも、マネーフォワードMEをうまく使えば、
1日1分の習慣で正確な家計管理ができます。
💡継続のコツ
レシート撮影を“買い物の締め作業”にする
支出が減った月は「ご褒美」を設定する
グラフを見る時間を「ちょっとした楽しみ」にする
「お金を守る」ことを“苦行”ではなく“ゲーム”のように楽しむことで、
継続率はぐんと上がります。
予算設定と家計分析の実践

マネーフォワードMEの最大の魅力は、
単なる「支出の記録ツール」ではなく、家計を改善するための分析ツールであることです。
この章では、予算設定から支出分析まで、
「数字を見て終わり」にしないための実践ステップを紹介します。
効果的な予算設定の基本
まず、予算設定の目的は「無理なくお金を残す仕組みを作ること」です。
マネーフォワードでは、カテゴリごと(食費・光熱費・交際費など)に毎月の上限を設定できます。
💡基本ルール:
予算は“前月の支出実績”を参考に設定する
いきなり大幅カットせず、10〜20%の削減を目標にする
「必要経費」と「浪費」を分けて考える
たとえば、食費が月6万円なら、まずは「5万5千円」を目標に設定。
小さな成功体験を積み重ねることで、継続率が上がります。<h3>固定費と変動費を分けて考える</h3>
家計をコントロールする第一歩は、
「どこを削るべきか」を明確にすることです。
固定費(家賃・保険料・通信費など)は見直しに時間がかかりますが、
一度削減できれば効果がずっと続くのが特徴です。
一方、変動費(食費・外食・娯楽など)は日々の行動でコントロール可能です。
マネーフォワードの「カテゴリ別支出グラフ」を活用すれば、
どこにお金が流れているかを一目で可視化できます。
💡おすすめ設定例
固定費:家賃、保険、通信 → 毎月見直しリマインダーを設定
変動費:食費、外食、日用品 → 予算オーバー時に通知ON
マネーフォワードでの家計分析のやり方
マネーフォワードMEの「レポート」画面では、
カテゴリ別・月別・年間単位で支出の推移をグラフ化できます。
これを活用して、以下の3ステップで家計分析を行いましょう。
① 支出の偏りを見つける
「外食費が増えていないか?」「サブスクが増えていないか?」を確認。② 削減できる項目を特定する
例えば「コンビニ支出を週3→週1にする」といった具体的行動に変換。③ 翌月の予算に反映する
分析結果をもとに、次月の予算設定を更新。
このように「振り返り→修正→再設定」を毎月繰り返すことで、
自然と貯金が増える家計サイクルが完成します。
年間の家計分析で長期プランを立てる
月単位の管理に慣れたら、次は年単位の分析です。
マネーフォワードでは、過去のデータをもとに年間支出を集計できます。
📊 チェックすべきポイント
貯蓄率(年間収入に対する貯金の割合)
季節ごとの支出傾向(夏の電気代、冬の暖房費など)
ボーナスや特別費の使い道
これらを見直すことで、「年にいくら貯めるか」「どこに使いすぎているか」が一目で分かります。
年末にレポートを見返すだけでも、家計意識が驚くほど変わります。
家族・パートナーと共有して“チーム家計”に
マネーフォワードの「家族共有機能」を使えば、
夫婦やパートナー同士で家計を一元管理できます。
例:
夫:固定費(家賃・保険)担当
妻:変動費(食費・教育費)担当
双方の支出を共有して、月末にミーティング
このように“チーム家計”として運用すれば、
「どちらかが浪費している」ではなく「一緒に家計を整える」という意識に変わります。
教育費や住宅ローンなど、将来に関わる費用も共有しておくことで、
長期的な資産形成にもプラスに働きます。
家計分析を「数字の確認」で終わらせないために
多くの人が家計簿を続けられない理由は、
「入力して満足してしまう」からです。
しかし、マネーフォワードMEは**“使ったあとの行動”**が価値を生みます。
毎月のレポートを見て、
-
「外食費が減った」→ 家族でご褒美を
-
「貯金率が上がった」→ 投資や旅行資金に回す
というように、結果を“モチベーション”につなげていきましょう。
まとめ|マネーフォワードを“記録アプリ”から“家計改善ツール”へ
マネーフォワードMEは、現代の家計管理に最適なアプリです。
銀行・クレカ・電子マネーなどを自動連携し、
「お金の流れを見える化」するだけでなく、「使い方を変える」きっかけを与えてくれます。
💡ポイントまとめ
自動連携で入力の手間をゼロに
現金支出もレシート撮影でカバー
予算設定とグラフ分析で支出のクセを可視化
継続するほど“自分専用の家計データベース”が完成
大切なのは、「記録して終わり」ではなく、
毎月1回、レポートを見直して次の行動につなげること。
この習慣こそが、浪費を防ぎ、貯蓄を増やす一番の近道です。
よくある質問
無料版では連携できる金融機関が最大4件までですが、 有料版(プレミアムプラン)では無制限で連携可能です。 また、「広告非表示」「データ更新頻度アップ」「資産推移の長期グラフ」など、 本格的に家計を管理したい方にはプレミアムがおすすめです。
照明が暗い、影が写る、レシートが丸まっていると文字が読み取れません。 明るい場所で平らに広げて撮影すると認識率が上がります。 長いレシートは2回に分けて撮るのがコツです。
金融機関側のメンテナンスや通信混雑が原因のことがあります。 少し時間をおいて再同期を試すか、「連携を再設定」すると改善する場合が多いです。 頻発する場合は、マネーフォワード公式の連携状況ページで最新情報を確認しましょう。
はい。2025年9月より提供開始された「シェアボード」機能を使えば、
家族やパートナーと安全に家計情報を共有できます。
ホスト(プレミアム会員)がシェアボードを作成し、
ゲスト(無料会員またはプレミアム会員)を招待することで、
口座やカード情報、支出・資産状況を同じ画面で確認可能です。
この仕組みにより、アカウントを共有する必要はありません。
それぞれが自分のアカウントを持ち、共有範囲を選択できるため、
プライバシーとセキュリティの両立が実現します。
📘 出典:マネーフォワード公式リリース(2025年9月16日)
次のステップ
ここまで読んだあなたなら、すでに家計管理の基礎は完璧です。
あとは、自分の行動をアプリに反映させるだけ。
✅ ステップ1:金融機関を連携
✅ ステップ2:予算を設定
✅ ステップ3:1か月使ってグラフを分析
✅ ステップ4:翌月に改善目標を設定
このサイクルを3か月続ければ、
「お金が貯まる仕組み」が自然と出来上がります。
そして次のステップとして、
👉 **「マネーフォワードME プレミアムプラン」**を試してみるのもおすすめです。
自動更新・資産グラフ・家族共有など、より高度な管理が可能になります。
まずは無料で自動連携を体験:銀行やカードをつなぐだけで家計簿が自動作成。
連携数や更新頻度を上げたい人はプレミアム体験がおすすめ。


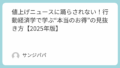
コメント