【結論】
人は「損のニュース」には過剰に反応しやすく、一方で「静かなお得」には鈍感になりがちです。
これは損失回避バイアスや群衆心理が働くためです。
だからこそ、周囲に流されず、“確率高く得を積む行動”を仕組み化するのが最適解です。
ぶっちゃけ、静かにやった者勝ちです。
1. きっかけ(実体験)
ミスタードーナツの「レシートアンケートで、253円以下のドーナツ・パイ・マフィンが半額になるキャンペーン」や、GODIVAの「ショコリキサー1個購入で1個無料」など。
店頭でしっかり掲示されていたのに、実際に使っている人はほとんど見かけません。
一方で、「値上げラッシュ」といったニュースが流れると、周囲が一斉に動き出す。
この“反応の差”を見て、正直「もったいないな」と感じました。
(※キャンペーン内容は店舗・時期によって異なり、不定期で実施されています)
2. なぜ“損”には敏感で、“得”はスルーされるのか
2-1. なぜ「損」には敏感で「得」には鈍感なのか?|損失回避バイアスの罠
人は「得をする喜び」よりも「損をする痛み」を約2倍強く感じる傾向があります。
これを損失回避バイアスと呼びます。
そのため、ニュースで「値上げ」「価格高騰」といった“損”を連想させる情報が流れると、私たちは過剰に反応してしまいます。
一方で、ミスタードーナツの半額キャンペーンやGODIVAの1個無料など、“得をする”情報には感情があまり動かず、見逃してしまうことが多いのです。
2-2. 周りの行動につられる理由|群衆心理(ハーディング)の正体
人は他人の行動を判断基準にしやすい生き物です。
たとえば「周りが買いだめしているから自分も買う」「誰も使っていないキャンペーンは不安だからやめておく」といった行動は、**群衆心理(ハーディング)**によるものです。
社会的な手がかりを頼りに行動することは一見安全に思えますが、冷静に考えると“得のチャンス”を逃す要因にもなります。
つまり、「周りがどうしているか」よりも「自分にとって合理的か」で判断する視点が重要です。
2-3. “ちょっと面倒”が得を逃す?|行動コストの壁とは
QRコードを読み取ってアンケートに回答し、次回来店時に提示する──。
このようにワンクッション手間が増えるだけで、利用率は大きく下がります。
これは心理学的に「行動コスト」と呼ばれる現象で、たとえお得だとわかっていても、わずかな“面倒くささ”が行動を妨げます。
つまり、「得を逃す理由」は“無関心”ではなく“行動のハードル”にあるのです。
お得を確実に活用するには、「少しの手間を習慣化する仕組み」を作ることが鍵になります。
たとえば、アンケート回答を家族で分担したり、次回訪問のリマインダーをスマホに設定するなど、“面倒”を自動化する工夫が効果的です。
3. 値上げニュースの“典型例”:「エッグショック」に見る心理反応
2025年10月後半、日本では今季初となる高病原性鳥インフルエンザが北海道・白老町の採卵鶏農場で確認されました。
約45.9万羽の殺処分が報じられ、各メディアでは「卵の価格が記録的水準に接近」との見出しが相次ぎました。
このような“値上げ懸念”ニュースは、まさに損失回避バイアスと群衆心理を強く刺激する典型例です。
実データの目安:
・実際のデータ動向(2025年10月時点)
📊 実際のデータ動向(2025年10月時点)
- 東京地区の9月平均卸売価格(Mサイズ)は1kgあたり約320円で、9月としては過去最高水準。
- 10月に入っても325〜335円付近まで上昇し、記録的高値圏が意識されています。
(出典:TBS NEWS DIG、全農たまご市場動向より)
🔍 背景要因の整理
背景要因の整理
- 飼料・燃油価格の高止まり
- 夏季の猛暑による採卵率低下
- H5系鳥インフルエンザの再燃
これらが複合的に重なり、国内外で“エッグショック再来”への警戒が高まっています。
(参考:Reuters/日本農業新聞/Nippon.com)
4.「静かに得している人」の動き方
「お得情報を知っていても行動できない人」と「確実に得している人」の違いは、仕組み化できているかどうかにあります。
“静かに得している人”は、偶然ではなく再現性のある行動パターンを持っています。
4−1. 小さな得を拾う習慣を持つ
店頭POPやレシートのQRコード、アプリ通知など、“気づけば使える小さな得”を逃さない。
例:ミスタードーナツのレシートクーポン、GODIVAの(例:1個買うと1個無料=B1G1(Buy One Get One)キャンペーン)など。
4−2. 一度やった“面倒”を仕組み化する
一度アンケートをやったらリマインドを登録、家族で分担、テンプレート保存など。
“やる気”に頼らず“仕組み”で行動を継続することがコツ。
4-3. 得を“次の得”に再投資する
浮いたお金を「次の家計改善」に使う。
たとえば、節約分を定期預金・積立投資・通信費の見直しに充てて“お得の連鎖”を生み出す。
5. 実践パッケージ(選択肢×優先順位つき)
「値上げニュースに踊らされず、静かに得を積む」ためには、
自分や家族の行動を仕組み化することが最も効果的です。
以下は、行動経済学と実体験に基づく3つの実践プランです。
5-1. 「静かな得」を家族内で仕組み化
レシート系キャンペーンやB1G1系などの“地味にお得”な施策は、
家族で役割分担すると効率が格段に上がります。
たとえば、月2回のレシートアンケートを家族で回すだけでも、
年間で約5,000円相当の得になる計算です。
行動コストが最小でリターンが早い、最も実践しやすい対策です。
5-2. 「買いだめ」は条件付きで行う
–卵のような劣化リスク・保管制約がある品は、消費計画と保存条件が整っている場合のみ限定的に。ニュースに合わせて衝動で積むのは非推奨。価格波形と特売日(曜日)を把握して“通常価格”を下げる方が効く。
参照:名古屋テレビ〖メ~テレ〗
5-3. 「代替・時期・地域」を分散して調達する
・代替食材をうまく使う(卵→豆腐・ツナ・おからなど)
・複数スーパーの特売曜日を分散してチェック
・近隣市の相場差を活用して“当たり所”を増やす
このような分散調達を意識すると、価格変動リスクを自然に抑えられます。
特に卵などの生鮮品は週単位で価格が変動するため、曜日ずらしが有効です。
6. ミクロ実装(仮説→実行→検証)
家計改善は「知識」より「仕組み」の実装が鍵です。
ここでは、“静かな得”を日常の中で習慣化するための小さな実験プロセスを紹介します。
6-1. 仮説(Hypothesis)
「静かな得」を月2回実践するだけで、
一般的な“買いだめ戦略”よりも安定的に家計を改善できる。
この仮説は、行動経済学でいう**“小さな成功の積み上げ”**効果に基づきます。
小さな成果を繰り返すことで脳が「得行動」を強化し、浪費を減らす方向に自然と最適化されます。
6-2. 実行(Action)
- レシート系・B1G1キャンペーンを家族で共有
- 月2回の“得行動”を決めてリマインド設定(例:日曜の買い物後に実施)
- 得した金額を家計アプリやメモで可視化
💡ポイント:
数字で“得”を見える化すると、達成感が続きやすく、行動の定着率が上がります。
6-3. 検証(Review)
3か月後に次の3点を見直します。
| 検証項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 得の合計 | 半額・B1G1で得た金額の合計 | 実質的な家計改善額を把握 |
| 体感コスト | 手間・時間・管理の負担 | 継続可能性の評価 |
| 続ける施策 | 手間が少なく効果が高いものを選定 | 習慣化する |
この振り返りにより、“無理なく続く家計改善サイクル”が完成します。
7. まとめ(要点だけ)
・値上げニュースは「損」を強く想起させ、感情的な行動を引き起こしやすい。
・一方で、家計に本当に効くのは「静かな得」の習慣化(例:ミスタードーナツの半額キャンペーン/GODIVAのB1G1など)。
・「エッグショック」のような値上げ報道に焦って買いだめせず、特売曜日の把握・代替食材の活用・地域分散購入などで淡々と対応するのが合理的。
参考(最新報道の確認用)
・北海道・白老町で今季初の高病原性鳥インフル確認、卵価への警戒(時事系配信/Nippon.com 要約)
👉 https://www.shokukanken.com/post-25682/
・TBS:東京地区の9月平均卸値は1kg=320円(9月として過去最高)
👉 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/2198676
・FNN:10月17日時点で1kg=325円、記録的高値圏に接近(JA全農たまごデータ)
👉 https://www.fnn.jp/articles/-/947799
・名古屋テレビ:地域相場・特売曜日の具体例(実務目線の価格感)
👉 https://www.nagoyatv.com/news/?id=032614
※外部リンクは参考情報として掲載しています。リンク先の内容・更新状況は各媒体の最新情報をご確認ください。
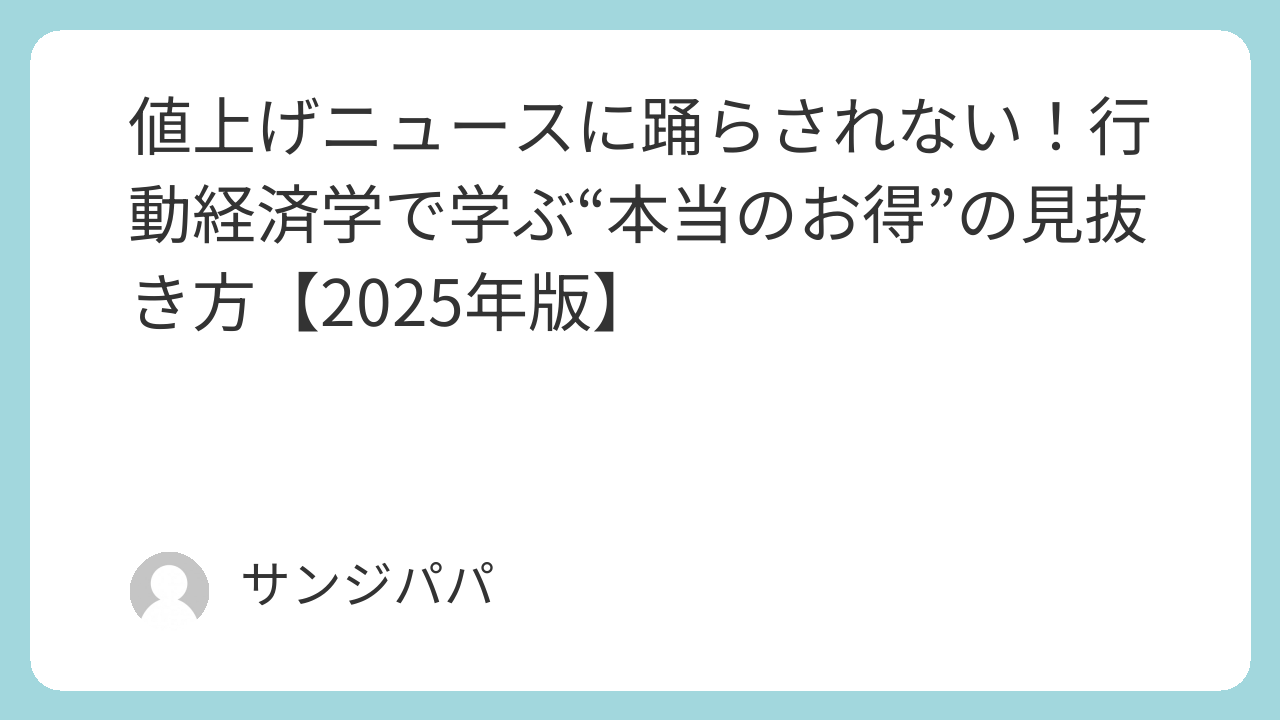


コメント